-
2011.07.28
DM紹介2011夏のDMお送り致しました。
ここ数日涼しいですね。最近の気候を夏と呼ぶのならありがたいのですが、その内また暑くなるのでしょう。 久し振りのブログです。今年の夏は例年以上に忙しくてなかなか更新できませんでした。 ハイ。言い訳ですね。 ペットシッターのストローラーカンパニーをご利用の方のお手元には届いているかと思われますが、先日夏のDMをお送り致しました。 お気に召していただけたでしょうか? 今回お願いしたイラストレーターはetoさん。可愛らしく、ストーリーのあるイラストを描いて下さいました。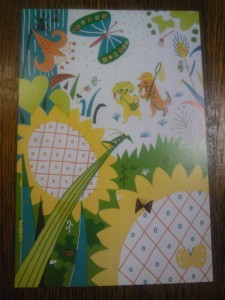 etoさんによると「濃い緑や、いろんな生き物のエネルギーがみなぎる夏、わんぞうと、ネコのにゃんたの夏休みのワンシーンというイメージ」だそうです。
etoさんに今年のDMをすべてお願いしたので、次回もわんぞうとにゃんたが登場するのでしょうか?
今から楽しみです。
etoさんによると「濃い緑や、いろんな生き物のエネルギーがみなぎる夏、わんぞうと、ネコのにゃんたの夏休みのワンシーンというイメージ」だそうです。
etoさんに今年のDMをすべてお願いしたので、次回もわんぞうとにゃんたが登場するのでしょうか?
今から楽しみです。 -
2011.06.30
ブログ -
2011.06.02
ブログアール・ブリュット・ジャポネ展に行ってきました。
ヘンリーダーガー展に行ってきたと前々回に書きましたが、そこで見つけたのがアール・ブリュット・ジャポネ展のチラシ。 パリで開催されたアール・ブリュット・ジャポネ展の様子はNHKで放映されていたのを見て興味を覚えてたのですが、日本に凱旋していたとはつゆ知らず。 どんな展示かといえば以下の通り(埼玉県立近代美術館のサイトより抜粋)アカデミックな美術教育を受けていないひとたちが生み出すかたち。自由な発想と創るよろこびに充ちた作品には、人間の純粋な創造性を垣間見ることができます。文化の違いを超えて観るひとの心をとらえるアート、それが「アール・ブリュット(生〈き〉の芸術)」。2010年に国内から63人の作家が参加してパリのアル・サン・ピエール美術館で開催された好評の展覧会が日本に凱旋。
これは面白そうだと埼玉県立近代美術館へ。美術館まで20キロも無さそうなのでチャリで向かう。 この日はとても暑くて、あっと言う間に背中に汗が。しかも外環脇の道は坂道が多くより発汗。 汗をふきつつ「暑い。暑い。」「お!ユニオンだ」とか呟きながらなんとか美術館に到着。 近代美術館は北浦和公園という大きな公園の中に併設されていて、公園の木陰は暑さを和らげてくれた。 ヘンリーダーガー展とは場所(原宿)が違うからか、会場内は年配の方が多い。作品自体の魅力は負けず劣らずなんですねけどねぇ。 作品の半分以上を見終えた頃に先生達に引率されて養護学校?の生徒さん達が入って来たのが印象的。 気になった作家を幾つか上げると本人は意図していないが故にマスコミ、商業主義に対する皮肉が利いている平岡伸太、M.K.、過剰に書き込まれているのに圧迫感が皆無でユーモラスな高橋和彦らの絵画、オシャレな上里浩也の飛行機やクレジットカードの模型・・・・ 上げていくと切りがないのですが、中でも一番気に入ったのは魲(すずき)万理絵の作品です。 とにかく絵に迫力が有るし、単純に巧いのです。彼女は元々絵心があって勤めている会社のニュースレターの挿絵をイラスト風タッチで描いているそうで、「なんで今の自分の(性器や鋏をモチーフとして多用する)スタイルで描かないの」と訊ねると「見た人がビックリするでしょう」と答えたそうです。 つまり彼女は仕事と自分の思いのままに描く作品を書き分けられる。この点は恐らく他の作家達とは違うはず。 その意識の差が彼女の作品をより魅力的なモノにしているのでしょう。そう考えるとアール・ブリュット「生の芸術」の概念から外れるような気もします。 そのような絵画絵画した作品にこの期に及んでも魅力を感じてしまのうか、自分はっていう感じもしますがいいモノはいいので。 たしかNHKの番組でもパリでのアール・ブリュット・ジャポネ展の主催者は魲さんの作品が展示のコアだと語っているように記憶しています。 上で述べたように作品自体とても面白かったのですが、ついついどんな人が作っているのかという背景が興味が移ってしまうのは邪道なのでしょうか? まあ、背景に目がいってしまうのは絵でも小説でも音楽でも一緒なのですが。アール・ブリュットにおいては特に。 でも作品のキャプションにもカタログにもその欲求を大いに満たす配慮はなされていて、そこをだけを読んでも興味深い。 施設の職員に恋をしてしまった途端に作品を作るのを止めてしまう人や作品を作る事自体より、作品に施設の職員を登場させた事実を伝える事に熱心な人等様々なエピソードが記述されている事を考えると背景に興味を持つ人はきっと沢山いるのでしょう。 展示されている作品を眺めていると性への興味、乗り物に対する偏愛、メディアからの影響等一般人となんら変わらなくて、アール・ブリュットだ、アウトサイダーだと殊更「差」を強調しなくてもいいのかなというのは強く感じしました。 最後に常設展にチラリと覗いて帰りました。ピカソやレンブラントが有りましたが、今村紫紅の掛け軸が一番面白かったです。 -
2011.05.27
ブログ -
2011.05.20
ブログヘンリーダーガー展に行ってきました。
先日、原宿はラフォーレで開催されていたヘンリーダーガー展に行ってきました。 アウトサイダーアートと言えばまず頭に浮かぶのはこの人。というか他の人を勉強不足で知らないだけですが。 アウトサイダーアートとは正規の美術教育を受けていない人が作った作品のことです。 アートにインもアウトも無いような気がしますが、音楽のジャンル分けしかり。カテゴライズした方がすんなりと世の中に受け入れて貰えるのでいた仕方無しですね。 どんな展覧会かと言えば、以下公式サイトより抜粋。家族も友人もなく、天涯孤独に生きたヘンリー・ダーガー。彼はその侘しい実生活を棄て、自身が夢想した物語『非現実の王国で』の中で生き、そこで起った出来事を、生涯を賭して記録しました。 ダーガーにとって『非現実の王国で』を綴り描くことは、人に見せるためでも、余暇の楽しみでもなく、生きることそのものでした。この特異な創作は、下宿先の大家夫妻によって偶然に発見され、彼の死後、人々の目に触れることになりますが、その不可思議な世界観と強烈な表現欲求は観る者を圧倒し、魅了し、心を捉えて離しません。 しかし、この物語を生み出したダーガーという人物は多くの謎に包まれたままです。彼は一体何者で、何を考えていたのか?何を愛し、求めていたのか?心穏やかに最期を迎えることができたのか?など、多くの謎が残されているのです。 彼が人生の後半40年を暮した部屋から見つかった遺品や書き物を手がかりに、ヘンリー・ダーガーの虚実に迫ります。
という訳でラフォーレへ。場所柄、若い人が多かったですね。作品も今っぽいので人気が有るのでしょう。 会場の平均年齢を一人上げつつ(笑)見て回りました。印刷されたものは何点か見たことがあるのですが、実際に見るとトレースやコラージュー具合が分かって面白かった。 トレース、コラージューの多用はPCで作られた現在のイラストと似ているような印象を持ちました。 それと思っていたより横長でデカイのです。(大きいものだと3mを超える) 彼の絵画は「非現実の王国として知られる地における、ヴィヴィアン・ガールズの物語、子供奴隷の反乱に起因するグランデコ・アンジェリニアン戦争の嵐の物語」という長いタイトルを持った小説の挿絵なので一枚一枚にストーリーが有るので、その横長の作品群は絵巻のもののようでした。 つまり絵を端から端まで見ていくのが楽しい。 その点では、お土産のポストカードの横長バージョンはセット売りのみでをバラで売らないのはどうかと感じました。画集は横長なのだろうか?縦長だと魅力を損なう気がするのだが。 ヘンリーダーガーがこのような作品を書いていることは誰にも知らず、死後彼の大家夫妻が作品を発見した訳ですが、大家さんのネイサンラーナーは画家。(奥さんは日本人!)この人がヘンリーダーガーを「発見」しなければ作品は捨てられしまったことでしょう。 そっちのほうがヘンリーダーガーにとって幸せだったかもしれません。彼は誰かに見せる為に作品を書いたのではなく、止むに止まれぬ怒り?性欲?願望?らをごっちゃにした衝動で描き続けただけだから。 この点が職業として作品を作り続けざる負えない人達から支持されるのでしょうね。 この展覧会で初めて知ったのですが、晩年、体力が落ちたヘンリーダーガーは大家さんに頼んで老人ホームを手配して貰い、そこで人生を終えた。彼が長年妄想を温めていた部屋「非現実の王国」ではなく。 ヘンリーダーガーは調子を訊ねられると「明日には風が止むかもしれません」と答えていたそうです。(毎日の天候に彼はとても関心が有った) 彼の人生に吹き続けていた冷たい風は果たして止んだのでしょうか?



